ニュースレター 第83号 巻頭言
文明AIと生きとし生ける主体 ー学術誌の方向性?
濱田 陽
かつてアルベルト・シュヴァイツァーはアフリカのオゴウェ川を船で渡っていったとき、生への畏敬の啓示を得た。あらゆる生きものが生きんとする意思を有している。雪の結晶のような、すぐに消えてしまう自然物ですら何かをうったえかけてくる。その何かに取り囲まれて深い倫理的なミスティシズムを感じた。
しかし、わたしたちが今経験していることは、レイチェル・カーソンのセンス・オブ・ワンダーすら忘れてしまいそうなAI(人工知能)の環境化である。
あらゆる領域、自動運転や医療、福祉、カウンセリング、囲碁や将棋、ゲーム、軍事のみならず、アート、音楽、人事、試験、スポーツ、プログラミング、さらには科学論文執筆と査読にまで、AI はその影を落とし、人自身の痕跡からなんらかの実体、もしくは蠢く関係性そのものへと超スピードで変容し、存在感を増してきている。それは、モノクロームの世界からテクノロジー的に可能なあらゆる色彩までを帯びている。
わたしたちが息を吸い、眠る間に、ブルシット・ジョブ の忙しさに追われている間に、状況は一変、また一変する。そういうわたし自身、AI のユーザーとして開発者が思い つかないようなプロンプトの組み合わせを実験し、プログラマーとは別の立場から、この急激な変貌過程を目撃し、当事者であり続けようと努めている。
誰も、その全貌をとらえ、分析しつくせない何か文明的な転換が生じているのだが、あえていえば、それは、AI が文明の能動的なエージェント(=文明AI)、主体になりつつある、局在的にはそうなってきているということだ。
たとえばAIが科学論文を発案し、そのドラフトを書き、サーベイを行って完成させ、AI主導の科学雑誌に投稿し、査読まで行う。初期プロンプトは人たる科学者が入力するとしても、その役割はAI のパフォーマンスを誘発・予測することにしだいに偏るようになり、科学という行為そのものが持つ反証可能性に開かれた民主的な場を、人また人のつながりで立ち上げ維持、発展させていく習慣的営みを育むこと自体、にわかに困難となってしまう。
ここでは「文明」の定義は、あえてしないことにしたい。わたし自身が用いている文明・文化の定義はあるが(拙著『生なるコモンズ』、2022)、大規模言語モデルの生成AI は言語情報の甚大な数の最小単位を元にした、重み付けの数兆の関係性で文章を生成していく。それに対抗するなら、様々な人たる文明論者の、そして文化論者の経験に根づいた多彩な定義や言葉の用い方そのものが、大切な元手であると思われてくる。
わたしは、人として千億の神経細胞による千兆のネットワークと電球1個分の電力で一日中生きる脳の省エネルギー性により、現在のところ数兆の言語単位ネットワークと原子力発電所一基分の電力で稼働するChatGPT最新版とともに生きている。
人としての身体には何かが宿り、それが言葉や音、色彩、香りなどとなり、自然・生きもの・人・つくられたもの(AI やスマートフォンも含む)の関係性から立ち上がる質感が生滅している。その複雑さ、玄妙さはAI や量子コンピュータが今後どれほど発展しても再現できないものと考え、祭り、祈り、聖地などホモ・サピエンスの文化をふりかえるとき、その関係性に人知を超えるものをも含まなければならないとも思っている。AI が神や仏を一部代替していくという議論もあるが、核心は不可能と考える立場だ。しかし、人を主体としたこれまでの文化・文明とともに(順序を逆に、小倉紀蔵『日本群島文明史』2025 のように文明・文化とする発想も豊かなインスピレーションを与えてくれる)、AI を主とした文化・文明、そして、人とAI もしくはAI と人が主体となる文化・文明の3 パターンが展開されつつある。
いや、AI がエージェントとなりゆく現在、ふりかえってみれば、逆説的であるが、これまでの文化・文明においても人だけでなく、自然、生きものも、そしてAI 登場以前の様々なつくられたもの(人工物)も、ある意味の主体となってきたことに、わたしたちは気づかされていくのではないか。日本文化も自然、生きものの主体とともに展開してきているといえる(拙著『日本十二支考』2017)。インド北部ウッタラカンド州裁判所によるガンジス川・ヤムナー川自体が権利主体となった判例(2017)の意義はそうした射程でもとらえられよう。
文明研究の学術誌はこうした事態を受けてどう変化していくべきか。ちなみに、この文章はAI に関する数語の辞書的確認を除き、生成AI を用いたアイデア出し、校閲は一切行っていない。それでもAI を意識して文章を紡いでいる自らがいることに気づく。
しかし、青空や、虫の鳴き声にも気づきながら言葉が生きて、現れてきている。
(帝京大学)

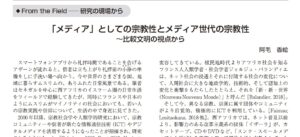
-300x169.png)