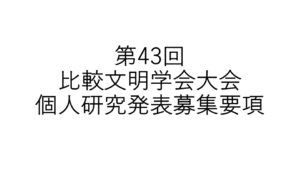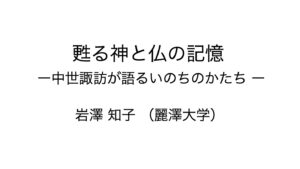第43回比較文明学会大会概要
第43回比較文明学会大会概要
1.日程
2025年12月20日(土)・21日(日)
2.会場
早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田1-6-1)
3.大会テーマ
文明の調和と共生の可能性―日本の「近代化」に関する比較文明学からの再検討
4.大会趣旨
周知の様に日本の「近代化」は、「西洋(とりわけ西欧)文明化」として語られる。こうした意味での「近代化」は、他のアジア地域に先駆けて実現した。この点に関しては、これまで様々な研究を通じて多方面から検討されてきたものの、未だ十分解明され尽くしてはいないといえる。というのも、従来の「近代化」に関する研究は、個々の領域の具体的研究が主であり、それらを比較文明学的な総合的な視点から検討するという試みは、必ずしも十分なされてこなかったからである。
今回の大会では、日本の「近代化」・「西欧文明化」の過程を比較文明学的な視点から考察したい。特に、異なる文明の移転・定着から変容の過程を、文明の生成・発展のダイナミズムの典型的な形態として、再検討を試みたい。こうした再検討から見えてくるのは、単純に「西欧文明化」としてだけでは理解し得ない複雑な移転・定着、そして変容のプロセスだろう。
日本の「近代化」は、明治期以降に突発的に起こった訳でなく、江戸幕府のもとでも徐々に進行していたともいえる。「鎖国」を実施したといわれもする江戸幕府のもとでの日本も、諸外国に対して閉ざされていた訳ではない。西欧の文化も様々な形で流入していた。国学者や攘夷派の論客も西欧の思想を吸収していた。一方で、明治期に、夏目漱石は、その文明論「現代日本の開化」の中で、日本の「近代化」を「皮相上滑り」のものと指摘した。それは、夏目から見て、内発的な近代化とは評し得ない実像であったからであった。さらに、日本の「近代化」の中には、王政復古の基盤を形作る中国文明など、複数の文明が伏在していたようにも見える。その中で、日本の文明はどのようなものとして形成されていったのか。そもそも固有のものとして存在し得たのか。
こうした日本における「近代化」を比較文明学的にどう評価すべきなのだろうか。本大会では、その総括を図ることにしたい。個々の専門領域の研究を踏まえつつも、総合的かつグローバルな視点から、日本の「近代化」について、そのダイナミズムを明確化する事を目指す。
5.プログラム
[第1日目 12月20日(土)]
(会場:早稲田大学早稲田キャンパス27号館地下2階 小野記念講堂)
10:00~12:00 役員会
12:30~ 受付開始
13:00~14:00
(1)基調講演
川勝平太氏(元静岡文化芸術大学学長)
〔基調講演では、川勝平太氏に日本の「近代化」に関して総合的かつグローバルな視点、つまり比較文明学の視点からご講演いただく。〕
14:10~16:30
(2)シンポジウム
テーマ:
「比較文明学からみた日本の『近代化』」(仮題)
司会:
金子晋右氏(佐賀大学教授)
シンポジスト:
島田竜登氏(東京大学准教授)、袁甲幸氏(早稲田大学講師)、小西暁和氏(早稲田大学教授)、保坂俊司氏(比較文明学会会長、中央大学教授)
〔シンポジウムでは、日本の「近代化」に関していわば実証的な視座から、経済領域について島田竜登氏に、政治領域について袁甲幸氏に、法律領域について小西暁和氏に、宗教文化領域について保坂俊司氏に、それぞれご報告いただく。〕
16:40~17:40 総会
18:00~20:00 懇親会
(会場:早稲田大学大隈ガーデンハウス3階)
[第2日目 12月21日(日)]
(会場:早稲田大学早稲田キャンパス8号館3・4階各教室)
9:00~ 受付開始
9:30~16:00 個人・グループ研究発表
6.参加費:会員3,000 円、学生会員・非会員500 円
7.連絡先:第43回比較文明学会大会実行委員会
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学法学学術院 小西暁和研究室
大会専用電子メール:jscsc43rd*gmail.com(*を@に読み替えてください)
※第43回比較文明学会大会個人研究発表およびグループ研究発表募集要項について
現在、大会2日目(2025年12月21日(日))における個人研究発表およびグループ研究発表の報告者を募集しております。会員の皆様より多数のご応募をお待ち申し上げます。詳細は、学会ホームページでご確認下さい。申し込み締切日は、2025年9月12日(金)23:00(締切厳守)となっております。
以上