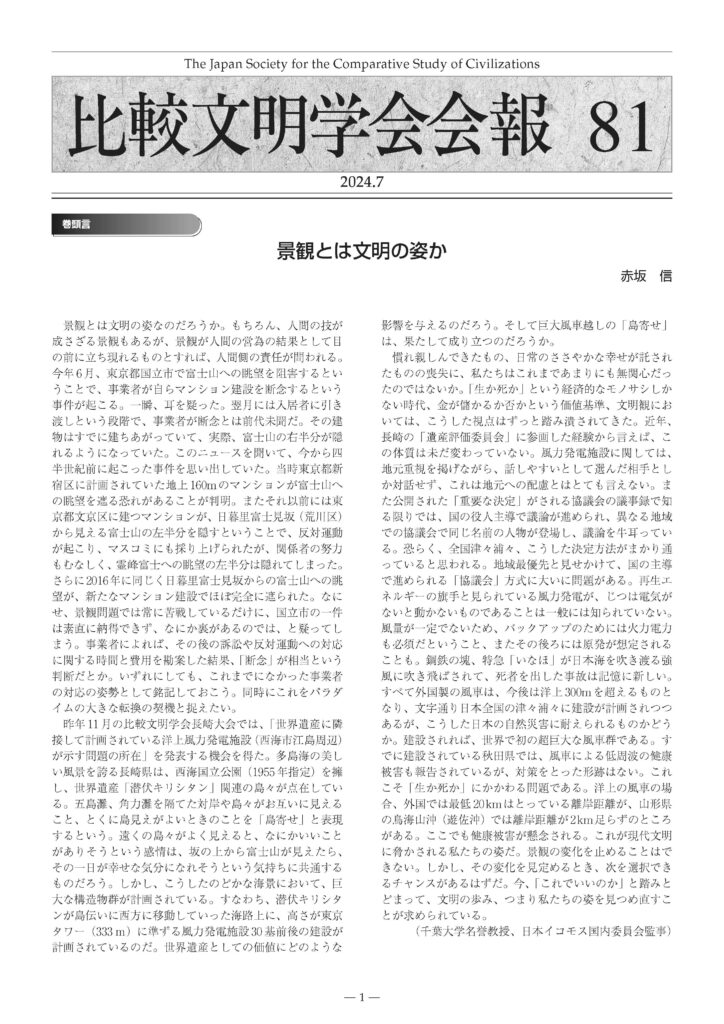ニュースレター第81号 巻頭言
景観とは文明の姿か
赤坂 信
景観とは文明の姿なのだろうか。もちろん、人間の技が成さざる景観もあるが、景観が人間の営為の結果として目の前に立ち現れるものとすれば、人間側の責任が問われる。今年 6 月、東京都国立市で富士山への眺望を阻害するということで、事業者が自らマンション建設を断念するという事件が起こる。一瞬、耳を疑った。翌月には入居者に引き渡しという段階で、事業者が断念とは前代未聞だ。その建物はすでに建ちあがっていて、実際、富士山の右半分が隠れるようになっていた。このニュースを聞いて、今から四半世紀前に起こった事件を思い出していた。当時東京都新宿区に計画されていた地上160mのマンションが富士山への眺望を遮る恐れがあることが判明。またそれ以前には東京都文京区に建つマンションが、日暮里富士見坂(荒川区)から見える富士山の左半分を隠すということで、反対運動が起こり、マスコミにも採り上げられたが、関係者の努力もむなしく、霊峰富士への眺望の左半分は隠れてしまった。さらに2016年に同じく日暮里富士見坂からの富士山への眺望が、新たなマンション建設でほぼ完全に遮られた。なにせ、景観問題では常に苦戦しているだけに、国立市の一件は素直に納得できず、なにか裏があるのでは、と疑ってしまう。事業者によれば、その後の訴訟や反対運動への対応に関する時間と費用を勘案した結果、「断念」が相当という判断だとか。いずれにしても、これまでになかった事業者の対応の姿勢として銘記しておこう。同時にこれをパラダイムの大きな転換の契機と捉えたい。
昨年 11月の比較文明学会長崎大会では、「世界遺産に隣接して計画されている洋上風力発電施設(西海市江島周辺)が示す問題の所在」を発表する機会を得た。多島海の美しい風景を誇る長崎県は、西海国立公園 (1955 年指定) を擁し、世界遺産「潜伏キリシタン」関連の島々が点在している。五島灘、角力灘を隔てた対岸や島々がお互いに見えること、とくに島見えがよいときのことを「島寄せ」と表現するという。遠くの島々がよく見えると、なにかいいことがありそうという感情は、坂の上から富士山が見えたら、その一日が幸せな気分になれそうという気持ちに共通するものだろう。しかし、こうしたのどかな海景において、巨大な構造物群が計画されている。すなわち、潜伏キリシタンが島伝いに西方に移動していった海路上に、高さが東京タワー (333 m) に準ずる風力発電施設30基前後の建設が計画されているのだ。世界遺産としての価値にどのような影響を与えるのだろう。そして巨大風車越しの「島寄せ」は、果たして成り立つのだろうか。
慣れ親しんできたもの、日常のささやかな幸せが託されたものの喪失に、私たちはこれまであまりにも無関心だったのではないか。「生か死か」という経済的なモノサシしかない時代、金が儲かるか否かという価値基準、文明観においては、こうした視点はずっと踏み潰されてきた。近年、長崎の「遺産評価委員会」に参画した経験から言えば、この体質は未だ変わっていない。風力発電施設に関しては、地元重視を掲げながら、話しやすいとして選んだ相手としか対話せず、これは地元への配慮とはとても言えない。また公開された「重要な決定」がされる協議会の議事録で知る限りでは、国の役人主導で議論が進められ、異なる地域での協議会で同じ名前の人物が登場し、議論を牛耳っている。恐らく、全国津々浦々、こうした決定方法がまかり通 っていると思われる。地域最優先と見せかけて、国の主導で進められる「協議会」方式に大いに問題がある。再生エネルギーの旗手と見られている風力発電が、じつは電気がないと動かないものであることは一般には知られていない。風量が一定でないため、バックアップのためには火力電力も必須だということ、またその後ろには原発が想定されることも。鋼鉄の塊、特急「いなほ」が日本海を吹き渡る強風に吹き飛ばされて、死者を出した事故は記憶に新しい。すべて外国製の風車は、今後は洋上300mを超えるものとなり、文字通り日本全国の津々浦々に建設が計画されつつあるが、こうした日本の自然災害に耐えられるものかどうか。建設されれば、世界で初の超巨大な風車群である。すでに建設されている秋田県では、風車による低周波の健康被害も報告されているが、対策をとった形跡はない。これこそ「生か死か」にかかわる問題である。洋上の風車の場合、外国では最低20 kmはとっている離岸距離が、山形県の鳥海山沖(遊佐沖)では離岸距離が2 km足らずのところがある。ここでも健康被害が懸念される。これが現代文明に脅かされる私たちの姿だ。景観の変化を止めることはできない。しかし、その変化を見定めるとき、次を選択できるチャンスがあるはずだ。今、「これでいいのか」と踏みとどまって、文明の歩み、つまり私たちの姿を見つめ直すことが求められている。
(千葉大学名誉教授、日本イコモス国内委員会監事)