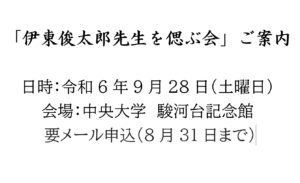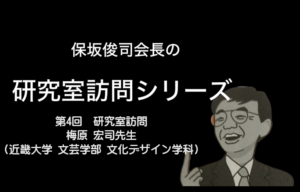第53回 国際比較文明学会 International Society of Comparative Study of Civilizations (ISCSC) 大会参加報告 エッセイ
慶應義塾大学 サイバー文明研究センター 研究員 佐野仁美
レスブリッジ大学、イニスキム (聖なるバッファローの石)
2024年5月21日から24日、第53回国際比較文明大会がカナダのレスブリッジ大学で開催された。国際比較文明学会(International Society of Comparative Study of Civilizations、以下ISCSC)はI961年に設立された。1995年から1998年には本学会名誉会長の伊東俊太郎先生が会長を務められた。また、昨年の長崎大会にはISCSC会長Lynn Rhodes氏と副会長Michael Andregg氏が来日された。本学会とISCSC間の比較文明学における長年の交流関係は、まさに日本と世界との架け橋である。
今年のISCSCの開催都市となったカナダ、アルバータ州レスブリッジは、19世紀後半から炭鉱業で栄えた都市である。現在レスブリッジはアルバータ州の第4番目の都市となっている。レスブリッジ大学は世界各地から生徒が集まる南アルバータで唯一の総合大学である。広大な敷地を持つキャンパスからは地平線が見渡せる。また、キャンパスは野生の鹿の生息地帯でもある。筆者はキャンパス内で、何匹もの鹿に遭遇した。

(レスブリッジ大学キャンパスの風景/ 筆者撮影)
カナダのアルバータ州とアメリカのモンタナ州をまたぐグレートプレーリー地帯は、歴史的にブラックフット族の領地であった。レスブリッジ大学はブラックフット族の伝統的な領地内にある。レスブリッジ大学はブラックフット族を含め大学コミュニティを支える先住民を尊重し、何千年もの間この土地を守り続けた先住民の知恵に深い敬意を払う。レスブリッジ大学はブラックフット族に由来する、Iniskim(イニスキム)という別名を持つ。イニスキムには、聖なるバッファローの石という意味がある。
学会の開会の挨拶はレスブリッジ大学ヘルスサイエンス学部長Jon Doan氏から歓迎の言葉があった。そして、ブラックフット族のElder. Young Pineが祈りを捧げた。Elder. Young Pineは先住民の言葉で学会の成功を祈った。参加者一同も目を閉じて共に学会の成功を祈った。

(祈りを捧げる Elder. Young Pine/ 筆者撮影)
今年のISCSCはレスブリッジ大学ヘルスサイエンス学部をパートナーとして開催された。今大会のテーマは「Health、Healing and Civilizations」である。数々の文明には、自己回復力を備えた文明がある一方、それを持たずに衰退した文明もあった。また、それぞれの文明の中には、健康と癒しに関する独自の知恵がある。今回の大会の目的は、文明の様々な健康と治癒という観点から、新しい研究やアプローチを推奨することであった。

(会場ホール前/ 筆者撮影)
コレクティブウェルネス、先住民のアプローチによる癒やし
学会開催の前日に、Nevada Lynn Ouelette氏(別名 Kihciihtwaw Asinewiskwew、聖なる岩の女性)による、先住民式のコレクティブウェルネスのワークショップが行われた。ワークショップには、地元の先住民やレスブリッジ大学の先住民の学生も参加した。彼らは、先住民コミュニティと一般社会の文化の違いを大きく感じていると述べた。ワークショップの主催者であるNevada氏は、カナダのクリー族にルーツを持つ。彼女は、先住民の豊かな文化的遺産を広め、先住民と一般社会の生活の間に感じるギャップを埋めようとしている。
Nevada氏のワークショップには、クリー族の「Sakihitowin」という「愛」に近い独自の価値観が取り入れられている。そして、このワークショップは、先住民と非先住民の相互理解を促進するだけでなく、様々なバックグラウンドを持つ人々を癒すことを目的としている。ワークショップには、様々な国から異なるバックグラウンドを持った約20名が集まった。
参加者はNevada氏が持参した、先住民族デザインのブランケットを囲むように座った。このブランケットは、過去から未来へと続く大地の時間の流れを表現している。ワークショップは先住民の歌から始まった。Nevada氏は、先住民にとって石は特別な意味を持つため、参加者に石を握りしめるよう促した。人間の生命より遥かに永い間、大地に存在した石が、個人のトラウマや不安を吸収して大地に還すそうだ。さらに、先住民の考えによれば、現在生きている人々の周りにはその人の先祖や子孫の魂が共に存在している。そのため、参加者が手に握る石が、先祖や子孫の心や身体の傷も吸収し大地に還すという。
人間は地球の大地を共有している、つまり大地はすべての人間の故郷である。大地に寄り添うことで人々の心が癒やされるのだろうかと筆者は感じた。しかし、ワークショップから癒やしの効果をまったく感じないと言う参加者も数名いた。

(ワークショップで使用したNevada氏のブランケット/ 筆者撮影)
確かに、Nevada氏のワークショップから得られる癒やしの効果は、すべての参加者に再現性があるわけでなく、個々の感受性や信念に大きく依存したかもしれない。しかし、先住民を含め、様々な文明には、家族、仲間、コミュニティを癒やし、維持するための独自の知恵が受け継がれてきたはずだ。これらの多くは、科学的に証明された効果や安全性を、あらゆる物事の拠り所とする現代的アプローチとは違う価値観が背景にあるのではないか。効能をどう感じるかよりも、まず先住民の文化や信念の中で、何が大切に培われてきたのかを理解することが不可欠だと筆者は感じた。
このワークショップからは、レスブリッジ大学が先住民の伝統的な土地に位置し、先住民との関係性を大切にし、文化や知識を尊重していることが伺えた。言葉だけでは説明しがたい先住民の知恵を、体験型ワークショップという形で広める姿勢に感銘を受けた。現代文明がますますグローバル化する中で、どの様に異なる文化や価値観を理解し尊重するかは、より重要性の高いテーマになるのではないかと考えさせられた。
ジャパン パネル

(ISCSC2024会場ホールの様子/ 筆者撮影)
学会の本編プログラムは、1) Civilization Panel、2) Japan Panel、3) Confucian Panel、4) AI Panel、5) Sorokin Panel、6) Health Practices Panelの6部で構成された。
筆者はジャパンパネル内で、「'Medical Inclusion' Health and Medical in the Global Digital Civilization」というテーマの発表を行った。慶應大学がネットワークを提供した日本-シンガポール間の遠隔手術教育や、コロナ禍で加速した遠隔医療システムなどを例に、デジタル技術が人間の健康と医療に影響を与えると紹介した。そして、情報技術と社会設計の連続性が、生命観にまで影響を及ぼす可能性を述べた。これまではビジネス分野の競争を背景にデジタル社会がグローバルに成長した。しかし情報文明では、すべてのインターネット参加者にとっての健康と医療の姿を改めて検討すべきであると述べた。その上で、インターネットのアーキテクチャを通じ、グローバルに共通する新たな医療と健康の社会通念を構築する必要があると強調した。
去年ご逝去された伊東俊太郎先生へ哀悼の意を示した上で、伊東先生のご著書から西洋科学文明下での生命観を紹介した。伊東先生は、西洋科学文明の土台となったデカルト、ベーコンの生命観を排除した機械論的自然観の欠陥を指摘されていた。さらに、その生命観を土壌として環境破壊や地球危機が引き起こされると警鐘されていた。そして、筆者の発表は、西洋科学文明における人間中心の「死せる自然観」から脱して、情報文明では地球規模のデジタル環境に新たな生命観を取り入れる「メディカルインクリュージョン」を提案した。
ジャパンパネルでは他にも、多様なテーマが取り上げられた。Robert Bedeski氏は、自身の独自の文明論を通じて、日本の自己治癒を伴う特殊な文明構造を説明された。Gideon Fujiwara氏は、和歌を通じて日本の健康についての統計や分析を紹介された。さらに、Aki Kinjo氏は日本企業の企業博物館に焦点を当て、世界を代表する日本企業のメンタリティを分析された。これらの議論をまとめたのは、ワシントン大学のYong-Chool Ha氏である。Ha氏は「Health for whom?」という質問を投げかけ、それぞれの発表における健康の想定範囲の違いを指摘された。ジャパンパネルの議論は、大会全体に深い印象を残した。その他のパネルでは、加藤久典先生によるインドネシアを始め、カナダ、中国、シンガポールなど、様々な地域やテーマに関する報告が行われた。
Head-Smashed-In Buffalo Jump、数千年続いたバッファロー狩り
学会の最終日には、有志の参加者がバスで真西に約70km進み、レスブリッジ大学のチームが発掘調査を行うHead-Smashed-In Buffalo Jumpの発掘現場に向かった。

(レスブリッジ大学キャンパスを出発するバス/筆者撮影)
ユネスコ世界遺産であるHead-Smashed-In Buffalo Jumpは、先住民の歴史やアイデンティティを理解する上でも重要な場所である。レスブリッジ大学の考古学者、Kevin McGeough氏から発掘プロジェクトの説明を受けた。公式には約6000年前からの先住民族によるバッファロー狩りの場とされているが、発掘現場からは約一万年前のものとも推定されるバッファロー狩りの道具が発見されているという。発掘調査チームの学生の一人が、昨日は約500年前の土器が見つかったが、500年前のものでは新しすぎるので残念だという感想を聞かせてくれた。

(レスブリッジ大学の発掘調査チーム、Head-Smashed-In Buffalo Jumpにて/ 筆者撮影)
Head-Smashed-In Buffalo Jumpの一帯には、数百メートルの崖が続いている。崖の上では、先住民がバッファローや狼に化けてバッファローの巨大な大群を崖の端におびき寄せ、追い込む。視野が狭いバッファローは、崖の先にもまだ地面が続いていると錯覚し、走り続ける。その結果、バッファローの群れが崖の上から、頭からずらずらと崖を転げ落ち自死する。つまり、Head-Smashed-In Buffalo Jumpは、獲物の習性と現地の地形を熟知した先住民が効率の良い狩りをする舞台であった。

(Head-Smashed-In Buffalo Jump、バッファロー狩りの舞台となった崖/筆者撮影)
先住民族の組織的な協力により、この崖を利用した狩りは何千年も続けられた。崖の麓では、崖の上で追い込まれて頭から落ちてきたバッファローが、他の動物の餌食になる前に、素早く皮をはぎ、肉を切り分けたり煮込んだりする後処理が行われた。したがって、崖の下には、先住民が使用したナイフや鍋、バッファローの骨が何千年分も手つかずのまま地中に埋まっている。バッファローは先住民にとって豊富な栄養源であり、他の動物よりも好まれて乱獲された。現在この地域では、バッファローはほとんど見られなくなった。さらに、ヨーロッパ人との交流と、先住民のコミュニティで鉄砲が流通したことにより、何千年も続いたこの狩りの方式は、19世紀には消滅した。
ISCSCに参加し、筆者は初めて知る文化に直接触れ、様々な角度から文明を垣間見ることができた。何千年の歴史を持つ先住民の息遣いや協力関係、強い絆を感じることができた。バッファロー狩りの発掘現場を訪問したことや、先住民式のヒーリングワークショップなど、非常に貴重な体験であった。現地での体験や人々との出会いは、書物や座学からは得られないものである。また、筆者自身の研究発表や参加者との交流を通じ、日本で得た知識や経験を世界に共有することができた。そして、ISCSCでの体験を日本に持ち帰ることの重要性にも気づき、本エッセイを綴った。このような交流が、より良い地球文明の構築につながると期待したい。